IPB University (タンココ自然保護区視察)出張報告
当学部国際獣医教育研究センターの教員派遣事業により、表題の出張先を訪問したので報告する。
出張期間:2025/3/1~3/9
今回の出張目的
5年次キャリアアップ研修の候補地(スラヴェシ島タンココ自然保護区)の視察
IPB Universityの紹介
国立IPB Universityは同国農業系大学の最高峰であり、同校獣医学校も戦後も最初にインドネシア国で創立された獣医系学部の最上位校。近年農業系学部のみならず、医学部、経済学部などの新学部が次々と設立され、総合大学化している。このため、2年前に英語表記をBogor Agricultural UniversityからIPB University に変更した。現在東南アジア獣医系大学のハブ的な役割を担っており、スマトラ島およびマレーシアでの獣医学部ブランチの創設、海外留学生の受け入れも積極的に行っている。
当学部とは昨年、同校獣医学校(SKHB)との間でLetter of Intentを取り交わしている。
タンココ自然保護区の紹介
スラヴェシ島北部にある国定の自然保護区であり、クロザル(Macaca nigra),やメガネザル(Tarsius tarsier)などの絶滅危惧種が生息している。IPB Universityはドイツのミュンヘン大学と共同で Macaca Nigra Project ( https://macaca-nigra.org ) として調査研究を実施中である。また各国学生に対して年間を通して研修を実施しており、野生動物を研究する学生を受け入れている。日本からの渡航費を合わせると、約20万円程度で2週間の研修を受けることが可能である。昨年の訪問時、SKHB野生動物学講座のMuhammad Agil 教授よりこの研修についての紹介があった。そこで今回、本学部獣医学科5年次のキャリアアップ研修先として利用可能かどうか、現地での視察を行った。また今回、各教員の指導学生も帯同し(自費参加)、現地での実際の調査に参加した。
詳細は以下の通り。
2025 3/1夕方松山発。マレーシアクアラルンプールで乗り継ぎ、翌3/2昼前ジャカルタ着。Deny助教に空港まで出迎えていただき、ボゴールへ移動。午後ボゴール着。
3/3 IPB University SKHBのAmrozi学校長を表敬訪問。併せてAgil教授、Deny助教と州政府からの保護区内での活動に関する許可、及び現地での移動・宿泊について打ち合わせ。

3/4早朝ジャカルタ出発し、午後スラヴェシ島マナド・サムラトウランギ空港到着。ここで今回自然保護区内のアテンドをして頂いた研究者のRisma女史(IPB Univ. 動物学科卒)と合流し、北スラヴェシ州自然保護局を訪問。タンココ自然保護区は観光者も受け入れており、ツアーガイドなどによる野生動物観察ツアーも行われているが、保護区深部のエリアについては入区が制限されている。今回の保護区内での活動について説明し、入区許可証を発行して頂く。その後マナド市内から約100km離れたタンココ自然保護区へ移動。


北スラヴェシはイスラム教信者の多いインドネシアにおいてキリスト教信者の多い地域であり治安は良好。


3/5~3/6 Rismaさんおよび調査員の皆さんのMacaca nigraの調査に終日同行。観察は極めて近い距離から可能である。観察者(調査員)と動物との接触は厳禁。まれに若齢個体からちょっかいを出されても反応しない。調査者と動物の良好な関係が維持されている。訪問時はちょうど食物の多い時期であったが、昨年8月の酷暑期には森内の餌も減り、死亡個体も多かった由。その場合でも給餌はしない。

この調査は地元の自然保護活動グループ、ミュンヘン大学、及びIPB Universityの協力のもと10年前から実施されている。金銭的なバックアップはミュンヘン大学が行い、現地の調査員の給与や調査拠点の維持費などが支払われている。調査拠点は保護区内に3か所あり、メインのベースキャンプは調査員の住居および研究者の宿泊施設となっている。
調査員を含めたスタッフの数は約20名。交代で12群の対象群の調査にあたっている。毎日早朝から夕方まで各群1名の調査員が群れを終日追跡し、群れの位置情報、群メンバーの異動、群間の抗争、健康状態、及び糞便の採取などを行っている。群れの位置情報はGPSで測位した情報がPC上の地図にプロットされる。対照群の全個体は顔や指の特徴、尻の皮膚(性皮)の形状によって個体識別されている。集積されたデータは定期的にミュンヘン大学に送られる。糞便検査はベースキャンプでは実施できないため、マナド市内のマナド大学で週1回寄生虫検査を実施している。
 ベースキャンプでは電気の使用可能な時間が夕方からの4時間だけの為、この間にPCの充電などを行う。
ベースキャンプでは電気の使用可能な時間が夕方からの4時間だけの為、この間にPCの充電などを行う。
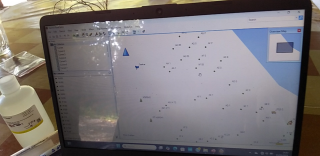 3/7 昼マナドを出発し空路ジャカルタへ移動。翌3/8ジャカルタを出発し帰国の途に就くも、遅延の為寄港地が変更となる。半日遅れたが予定日の3/9に帰国。
3/7 昼マナドを出発し空路ジャカルタへ移動。翌3/8ジャカルタを出発し帰国の途に就くも、遅延の為寄港地が変更となる。半日遅れたが予定日の3/9に帰国。
総括:キャリアアップ研修の受け入れ先としての可能性について
参加学生は、動物の個体識別法、追跡法、行動の分類やデータの採取法等についてレクチャーを受けながら調査員に同行し、実際に行動調査に参加することができる。IPB Universityや海外の大学の学生もこの調査に参加しており、彼らとの研究交流も可能である。またサマーキャンプでは地元小学生への野生動物の保護啓蒙のイベントも行われており、各国学生とともにこの活動に参加することができる。
研修に参加するのに必要な要件として、①ある程度の英語でのコミュニケーション(インドネシア語ができればなお良い)が可能であること②熱帯雨林での野外活動が可能な基礎体力と忍耐力③異文化に対する敬意と順応性を持っていること、を挙げておられた。
実際、我々も調査に同行してみて、動物の観察は容易であり、野生動物の研究の基礎を学ぶのに適していると感じた。加えて、日本とは文化も言語も環境も全く異なる場所での生活は、野生動物獣医学について学ぶ以外にも得られるものが多い。しかし旅行感覚で参加できる研修先ではなく、必要に応じて教員の同行が必要となるかもしれないが、真剣に野生動物について学びたい学生には魅力的な研修先だと考える。最後に今回このような機会を与えて頂いたことに感謝いたします。
報告者
獣医学部 獣医学科
産業動物臨床学講座 講師 井上陽一
野生動物学講座 講師 奥田ゆう







 ベースキャンプでは電気の使用可能な時間が夕方からの4時間だけの為、この間にPCの充電などを行う。
ベースキャンプでは電気の使用可能な時間が夕方からの4時間だけの為、この間にPCの充電などを行う。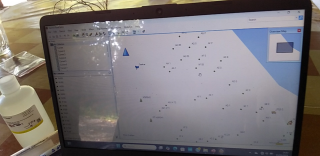 3/7 昼マナドを出発し空路ジャカルタへ移動。翌3/8ジャカルタを出発し帰国の途に就くも、遅延の為寄港地が変更となる。半日遅れたが予定日の3/9に帰国。
3/7 昼マナドを出発し空路ジャカルタへ移動。翌3/8ジャカルタを出発し帰国の途に就くも、遅延の為寄港地が変更となる。半日遅れたが予定日の3/9に帰国。